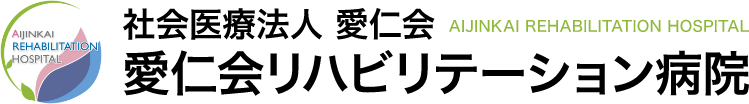看護部
看護部長挨拶

愛仁会リハビリテーション病院
看護部長 福井 希代子
私たち愛仁会リハビリテーション病院の看護部は、「もてる力を みつける 支える のばす」を理念に、看護を実践しています。病気やケガなどで体が不自由になられた患者さまの、身体や心理面、生活やご家族の背景などを把握したうえで、「もてる力」を見出し、少しでもご自身でできることを増やしていけるよう支援します。
“リハビリテーション”は、訓練でできるようになったことを、日常の生活の中で繰り返し練習しながら動作を獲得することが大切です。私たち看護職員は、リハビリテーションができる体であるよう栄養や睡眠など状態を整えながら、また、日常の生活動作が安全にできるよう見守ったり、介助をしながら支援していきます。そして、患者さまが、住み慣れた地域で安心して過ごせることを目標に、多職種が連携して医療を進めてまいります。
患者さまの思いを尊重しながら、専門職として入院中の生活、退院後の生活を一緒に考えたいと思っています。ご希望や意見、不安、疑問は遠慮なくお伝えください。

看護部理念
もてる力を みつける 支える のばす
看護部基本方針
- 患者さまのもてる力をみつけ、支え、のばし、患者さまやご家族の思いに寄り添った看護を実践します。
- リハビリテーション医療・看護の専門性を高め、安全・安心なケアの実践に努めます。
2025年度 看護部目標
-
リハ看護の充実を図る
1)患者状態から予測的に対応し、重症化を予防する
2)倫理的感性を高める
3)認知症患者の対応力向上を図る
4)患者の意思決定を尊重した看護実践を行う
5)ラダーを活用した人材育成を行う
6)介護福祉士の専門性を活かす -
ICFを活用した多職種協働の推進
1)身体的拘束の最小化を図る
2)「活動」を「参加」に繋げるチーム医療の強化を図る
3)適正な病床管理を維持する -
働きやすい職場環境の整備
1)対話を通じた相互理解を深める
2)メンタルヘルスの総合支援に取り組む
病棟の様子紹介
-

歩行介助
日常生活で行う更衣・靴を履く・立ち上がる・歩く・座る・手を洗う・歯磨き・食べる・話すなどの動きの中で、在宅復帰に必要な生活動作を訓練により獲得できるよう看護師がサポートしています。
病気やケガの急性期医療を乗り越えられた患者さまに、再びその方らしい生活を取り戻していただくために。私たち「リハビリナース」は、日々のケアや生活リハビリテーション、退院調整などを通じて、患者さまに深く関わり、寄り添い続けます。 -

新人「吸引」研修
人材育成に力を入れる当院ではOJTによる新人看護師臨床研修制度を設けています。
そこで大切にしているのは、相手を思いやる「仁のこころ」です。新人看護師は「患者さま」、先輩看護師は「新人看護職員」に対し心を寄せ、「観る・聴く・言う」をモットーに行動を起こす。
その上で看護の実践体験を科学的に思考すること、できたことをともに喜ぶことは、新人看護師はもちろん先輩看護師の精神面・技術面の成長にもつながっています。 -

新人研修
当院では看護技術の向上をめざし、日々さまざまな院内研修を実施しています。時には看護する側・される側に分かれた演習も行い、患者さまの立場を疑似体験することも。
こうした研修の積み重ねが、実際の看護の現場で生かされています。
また本人のやる気や希望に応える充実のキャリアアップ支援体制も用意。脳卒中リハビリテーションや認知症、感染管理、摂食・嚥下障害など、より専門的な知識と技術を有する看護師も多数在籍しています。
専門の看護師のご紹介
-

メッセージ
日本看護協会摂食・嚥下障害看護認定看護師
馬嶋 きみ代 主任
「口から食べる」ことは、人生の楽しみであり、日々の生活をより豊かにしてくれるもの。食事は決して生命維持のためだけではないと考えています。食べることに障害のある患者さまが再び口からおいしく食べられるよう、また安全に食べ続けられるようサポートするのが私たちの役目です。低栄養や脱水、誤嚥性肺炎など起こり得るトラブルを予防しながら、患者さまとそのご家族さまに寄り添い、精いっぱいの支援をさせていただきます。
日本看護協会摂食・嚥下障害看護認定看護師:馬嶋 きみ代 主任
-

メッセージ
日本看護協会認知症看護認定看護師
沼田 かおり 副主任
人は一人ひとり尊重され、大切にされる存在で、認知症を患っていてもそれは変わりません。人生の最後まで、その人らしく穏やかに過ごし、笑って暮らせる生活の支援を大切にしています。認定看護師は、身体、環境の変化に戸惑い、苦痛をうまく表現することが難しい認知症患者さんの心のつらさに寄り添い、安心して入院生活を送れるように病棟スタッフや主治医、多職種と協働して、患者さんとご家族の思いを支援する活動を行っています。患者さんとそのご家族、スタッフが笑顔で一日一日を過ごせることを願っています。
1995年京都保健衛生専門学校卒業。2024年から愛仁会リハビリテーション病院勤務。日本看護協会認知症看護認定看護師。日本看護協会認知症看護認定看護師:沼田 かおり 副主任
-

メッセージ
日本看護協会感染管理認定看護師
藤田 慧 室長
感染管理認定看護師は、患者さんやその家族、職員など病院に関わる全ての人を感染症のリスクから守るために、様々な活動を行っています。
よりよい感染管理を行うためには、専門的な知識や技術だけではなく、病院のこと、職員のこと、患者さんのことを正しく理解することが必要です。
患者さんと直接関わる職員がより質の高い感染対策を行い、よりよい療養環境を提供できることを目指し、ひとりひとりが持てる力を最大限に発揮できるよう、実践、相談、指導の3つの役割を果たして参ります。日本看護協会感染管理認定看護師:藤田 慧 室長
-

メッセージ
感染制御実践看護師
市橋 卓浩 科長
感染症による影響を最小限にし、一日も早い機能回復に取り組むことが再びその人らしい生活を取り戻すため必要なことです。感染対策を重点的に取り組んでいるリハビリテーション専門病院はあまりないといえますが、当院では感染対策チーム(ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(AST)が毎週、回診を実施。さらに病院だけでなく、周辺地域に対する感染対策施策も行っており、誰もが安心して在宅療養生活を送れるよう体制を整えています。
感染制御実践看護師:市橋 卓浩 科長
研修・取り組み紹介
専門的な知識と技術を要するリハビリテーション病院の看護師として、患者さまに本当に必要なリハビリテーション看護の習得のための院内研修会が多数行われています。
中でも理学療法士や作業療法士など多くのセラピストが在籍する当院の研修の特徴は、教育研修部が設置され、職種の垣根を越えた共同研修会を実施している点。通常セラピストのみが習う身体介助方法なども学ぶ機会があり、他職種ならではの技術にふれることはリハビリテーション介護を提供する上で大きな強みとなります。
さらに入職後の期間や年数に応じて段階的な教育を行う、当法人全体で開催される看護師の新人臨床研修も用意されています。また技術面だけでなく看護師に求められる高い倫理観の育成にも注力しているほか、患者さまの異常・異変に即座に気づくためのアセスメント能力向上に関する教育も強化中。
リフレッシュ研修として、障害者スポーツ「ボッチャ」体験なども取り入れています。


求職活動をしている方へのメッセージ
リハビリテーション看護は、「疾病・障害・加齢等による生活上の問題を有する個人や家族に対し,障害の経過や生活の場にかかわらず、可能な限りADLの自立とQOLの向上を図る専門性の高い看護」と日本リハビリテーション看護学会では定義しています。
卒後教育は、新人看護職員臨床研修がありますが、看護部独自の研修だけではなく、当院ならではのセラピストと一緒に受講する研修も多くあります。その後は、ラダー教育へ移行し、学研のeラーニング活用や対面式研修、ウェブ研修などを行っています。
実践では、当院の理念である「再びその人らしい生活に」の実現のために入院時・退院前訪問、地域との密な連携を多職種と協力して進めています。
さあ、患者さまの「もてる力を みつける 支える のばす」リハビリテーション看護を一緒にやってみませんか。